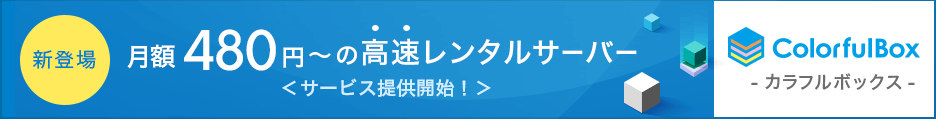
その男には東京を歩いているといつも膝まで水があがってきているように見え感じられるのだったが、同意してくれる人はいなかった。かれの目には東京の道路は川であった。
また、かれの目には東京を飛び交う電波はさまざまな色がついていてとても奇麗な見世物だったが、その呼び合う声はかれ以外のものには見えないのだった。
新宿のアルタ前の交差点を歩いていて、男はふと、金色のゆきが降り積もっていることに気が付いた。この雪はやすむことなく降り積もり、この街をうずめてしまうのだ、ということが数学的な正確さで理解できた。
くろぐろとした出所のしれない水に浸されて男は毎日出勤した。すると、ときに、東京を浸す水のなかにうつくしい人魚を見た。そのうつくしい顔はどこかで見覚えがあるものだった。
ある日男は電車に乗って新宿から東京へ向かっていた。
人魚がやってきてかれに話しかけた。
その言葉は理解できなかった。
だが記憶にない記憶が蘇り、理解できないままに男は人魚をだきしめた。胸から血が流れ、東京を浸す水を赤く染めて行った。
男はその水がかれの夜ごとの夢から漏れ出した石油のように黒いかげりであることを知った。
そして、時間がかけがねを失った。
犯人は山の手線のなかで突然目の前の偶然乗り合わせた女性に所持していたナイフで切り付け、致命傷を負わせた。現行犯逮捕したところ、精神の平常をうしなっているようなので病院に送られた。公判では心神喪失ということで罪にはならなかった。かれは恋人に堕胎させた子供のことでノイローゼぎみであったという。
人魚よ、たえなる人魚よ。
男はくらい水に溺れていた。
二十年後、男は回復したので世間に戻って来た。
だがかれが見たのは、もはや胸元まであがってきた水だった。
かれは笑い出した。
おれがころした人魚はおれの正気だったのだ、と、悟ったのだ。
ビルの谷間には滔々と大河が流れ、無数の、幼い人魚が幾千、幾万としぶきを散らして遊んでいた。
そして男は歩道橋から身を投げる。
死骸がかたづけられたあとには、黒い華が咲いた。
月夜には歌う。